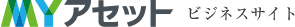市街化調整区域の土地が売れない?売却成功の条件と対処法を解説
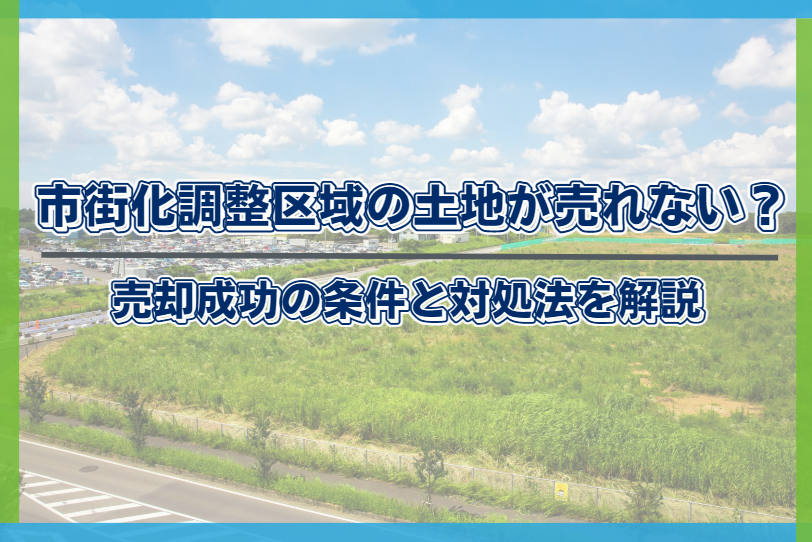
2025年9月3日
目次
市街化調整区域の土地は建築制限があるため、一般の宅地より売却が難しい傾向にあります。
買主が限られ、固定資産税などの維持費がかさむことから、処分を検討する方も少なくありません。
しかし、法令や地域制度を正しく理解し、適切な買主層を見極めて手続きを進めることで成約の可能性を上げられます。
本記事では、市街化調整区域が売却しづらい理由や確認すべきポイントについて解説します。
そもそも「市街化調整区域」とは
市街化調整区域とは、農地や自然環境の保全を目的に、建築や用途の変更が原則として制限されているエリアです。市街化区域とは異なり、住宅や商業施設などの建築は認められておらず、許可が下りるのは農家住宅や公益施設などに限られます。
こうした土地は郊外に多く、インフラが整っていないケースも少なくありません。その結果、一般の土地と比べて流通性が低く、売却しにくい傾向があります。立地やインフラの制約に加え、法的な規制も売却のハードルとなる要因のひとつです。
とくに売却を進める際は、建築の可否や買主の用途想定に加えて、農地法や都市計画法の適用状況を確認することが欠かせません。これらの情報を事前に整理すれば、具体的な売却戦略を立てることができます。
相続・放置された市街化調整区域の土地でよくある悩み
「売れない土地」に悩む相続人の声
相続で取得した土地が使い道もなく、放置されたままになっているケースは少なくありません。共有名義で意思決定が進まず、実勢価格との差に戸惑って売却のタイミングを逃す方も多く見受けられます。境界の不明確さや雑草の繁茂によって、管理費用や手続き負担が増えていくことも懸念点です。
税金負担と放置リスク
固定資産税は市街化区域よりも低い傾向にありますが、年数が重なれば負担も大きくなります。また、草木の放置や不法投棄などによって近隣トラブルや資産価値の低下を招くこともあります。適切な管理ができていない状態は、買主にとってもマイナス要因です。
「誰に相談すればいいか分からない」不安
市街化調整区域は法的制限が多く、通常の住宅売買を中心とした不動産会社では対応できないことがあります。過去に「取り扱えません」と断られた経験があると、次にどこへ相談すべきか分からなくなるのも無理はありません。
こうした土地の売却には、都市計画や法規制に詳しい業者を選ぶ必要があります。実績がある会社であれば、適切なアドバイスが期待できるでしょう。
市街化調整区域が売れにくくなる3つの主な要因
1.なぜ建築が制限され、買主が限られてしまうのか?
市街化調整区域では、新築や再建築が原則として認められておらず、建築が許可されるのは農家の分家住宅や公共性のある施設など、特定の用途に限られています。
このため、マイホームや収益物件を探している一般の買主とはニーズが合いにくく、検討される機会も少なくなります。
また、不動産投資を目的とした買主にとっても、建物の活用や転用が難しいことから、期待する利回りを見込みづらく、対象外となってしまうことが多いのが現状です。
ただし、特例区域に該当する土地や、既存施設との組み合わせによっては、活用の余地がある場合もあります。建築制限の内容を整理したうえで、どのような売却の形が望ましいかを検討するのが得策です。
2.金融機関の評価が低く、資金調達が難しくなる
市街化調整区域の土地は、再建築の制限や市場での流通性の低さから、金融機関による担保評価が低い傾向にあります。そのため、購入希望者が不動産投資ローンを利用しようとしても、融資が認められないケースが少なくありません。
ローンが組めない場合、買主は多額の自己資金を用意しなくてはならず、こうした資金面のハードルが、購入判断を妨げる要因のひとつ。
また、対応可能な金融機関が限られていることも多く、買主側にとっては資金計画が立てづらいのが現状です。
結果として、売却に時間がかかったり、価格交渉がシビアになったりすることから、市街化調整区域は売却しにくいのです。
3.インフラ未整備や接道不備がネックになる
市街化調整区域の土地では、上下水道や都市ガスといったライフラインが整備されていないことがよくあります。さらに、前面道路の幅員が狭く、建築基準法で定められた接道条件を満たしていない場合、セットバックなどの追加工事が必要です。
こうした整備にかかる費用は買主側の負担となることが多く、想定外のコストが発生することが購入を見送る要因です。
売却を検討する際は、事前にインフラの状況を確認し、必要な工事の内容や費用の目安を整理しておくと、買主との交渉が進めやすくなります。
市街化調整区域の土地を売却するために確認すべき4つのこと
1.区域指定エリアかどうか
市街化調整区域の中には、「既存集落」や「公益性の高い施設」の建築が認められる特例地域があります(都市計画法第34条第1号・第11号など)。こうしたエリアに該当する場合、建築許可が得やすくなるため、買主が活用できる可能性が広がります。
売却の検討段階で、まずは対象地がどの区域に該当するかを確認することが大切です。一般的には、市区町村の都市計画課で「区域証明書」を取得することで、詳細な区分を把握できます。
2.地目とその活用条件
登記上の「地目」も、売却を検討するうえで重要な確認項目です。農地(田・畑)の場合は農地法の制限を受けるため、転用や売却には申請が必要です。
一方、山林や雑種地は農地法の適用外ですが、宅地に変更する際には登記変更や開発許可を求められるケースもあります。
また、登記簿と現況が一致していない場合、買主の融資審査に時間がかかります。売却をスムーズに進めるには、現況・登記・公図の情報をあらかじめ照らし合わせておくとよいでしょう。
3.既存宅地要件の有無
昭和50年以前から住宅として利用されていた土地は、いわゆる「既存宅地」として建築が認められる可能性があります。現在は制度として廃止されていますが、個別に許可が得られるケースがあるため確認しておきましょう。
建築実績の証明には、課税記録や古地図、航空写真などの資料が必要です。該当すれば建築制限の緩和が期待でき、売却できる可能性が広がります。
4.上下水道などインフラ状況
上下水道、電気、都市ガスなどのインフラ整備状況は、買主の判断に影響します。例えば、引き込み距離が長ければ工事費用が増え、購入のハードルが上がる原因となります。
また、前面道路の幅が狭く接道条件を満たしていない土地では、セットバックや追加工事が必要になるケースも少なくありません。
こうした状況を踏まえ、自治体の台帳や図面から接続可否や工事条件を確認し、買主に伝えるべき情報をあらかじめ整理しておくと、交渉がスムーズに進められます。
市街化調整区域の土地は誰に売れる?想定ターゲットと価格の目安
買主ターゲットの傾向
1.農業従事者・農業法人
既存の農地を拡張したい農業従事者や、農業法人によるハウス栽培、資材倉庫の設置など、農地利用を前提としたニーズがあります。
2.建設・運送業などの法人
資材置き場や車両の駐車場としての用途で購入されるケースが多く、建築制限の影響を受けにくいため、比較的検討されやすい傾向があります。
3. 太陽光発電
市街化調整区域でも、地面に設置する野立て型の太陽光パネルなら設置が可能です。
事業者は日当たりの良い土地や広い敷地を好むため、通常は売却が難しい不整形地でも売却しやすくなるでしょう。
また、農地の場合、第2種・第3種なら転用許可を得やすく、さらに売却の可能性が広がります。
ただし、送電線への接続可否や景観条例については事前確認が必要です。
4.駐車場
平面駐車場は建築物を伴わないため、市街化調整区域でも利用しやすい活用方法です。
地元の運送会社や建設会社が、資材置き場や車両スペースとして購入を検討することも少なくありません。
立地によっては月極駐車場として利用されるほか、幹線道路沿いでは大型車両の待機場所としての需要も見込めます。
初期投資が少なく始めやすい事業ですが、接道条件や周辺の需要は事前に確認しておくことが重要です。
売却価格の目安
市街化調整区域の土地価格は、市街化区域の同等地の30%~70%程度ですが、実際には地域・地目(農地・山林・雑種地等)、インフラ整備状況、許可取得の難易度などによって大きく変動します。
実勢価格を把握するには、国土交通省公示地価の標準地データや路線価、REINS(不動産流通標準情報システム)の類似事例を比較検討してください。
市街化調整区域の土地を売却するための対応策
市街化調整区域に強い不動産会社を選ぶ
市街化調整区域は、建築や売却に制限があるため、通常の不動産会社では対応が難しいこともあります。
売却を検討する際は、市街化調整区域に関する法律や制度に詳しく、行政とのやりとりに慣れた不動産会社に相談することが望ましいと言えます。
「用途変更はできるのか」「どのような買主に向いているか」など、現地調査から手続きの段取りまで、具体的に説明してくれる担当者を選ぶことが、スムーズな売却への第一歩です。
農地転用や開発許可の取得
地目が「田」や「畑」の農地になっている場合、そのままでは住宅や事業用地として売却できません。この場合は「農地転用」と呼ばれる手続きを行います。
申請には、土地の利用計画や周辺環境への影響を記載した書類をそろえたうえで、行政との協議を進めていきます。
また、盛土や排水設備などの工事を伴うと「開発許可」も必要になるケースがあります。
こうした手続きは専門性が高いため、手続きを代行してくれる業者と連携するのが現実的です。
行政・自治体との連携活用
自治体によっては、空き家・空き地バンクという仕組みを用意しており、登録することで購入希望者とマッチングされる機会が得られます。
登録料が無料または低額のところも多く、民間の売却活動に比べて気軽に始められるのが特徴です。
また、地域によっては移住支援や農業体験などの取り組みに合わせて、買主側に補助金が出るケースもあります。
買主にとっての費用負担が軽減されれば、売却のチャンスが広がるかもしれません。まずは、所有する土地が制度の対象となるか、自治体窓口に相談してみるのがおすすめです。
売れない場合の選択肢
売却活動を行っても買主が見つからない場合、「どうにもならないのでは」と不安になるかもしれません。ですが、いくつかの選択肢を知っておくことで、気持ちの負担を軽くできます。
例えば、相続直後であれば「相続放棄」という方法があります(※手続きは相続開始から3カ月以内に必要)。
また、一定の条件を満たせば、土地を手放して国に引き取ってもらう「国庫帰属制度」を利用することも可能です。
他にも、将来的な売却を見据えて、草刈りや巡回管理などを業者に依頼し、土地を良好な状態で保っておくという方法もあります。
「売れない=終わり」ではありません。自分に合った対応策を少しずつ選んでいくことが大切です。
土地売却に関するご相談はMyアセットへ
Myアセットでは、土地売却をスムーズに進めるための多様なサポートを行っています。
・建築士など専門家による現地調査と図面の照合
・ドローン撮影やリモート接客など、非対面での柔軟な対応
・多数の金融機関との取引を活かした資金面での安心感
・活用提案や改修工事などを含めたワンストップ対応
物件の状態やエリアに応じた売却方法をご提案します。土地売却に関するご相談もお気軽にご連絡ください。
まとめ
市街化調整区域の土地には、建築制限や法的な制約が多く、売却が難しい側面があります。ただし、区域の種別や地目、既存宅地の要件、インフラ状況などを丁寧に確認することで、対応の方向性が見えてきます。
制度に理解のある買主層へ適切にアプローチすることで、成約の可能性を高めることも十分に可能です。相続や長期保有に関する悩みがある場合は、まず現状を正確に把握することから始めましょう。
そのうえで、必要に応じて許可の取得や自治体制度の活用を検討し、売却に向けた具体的な計画を立てていくことが大切です。
売却のご相談は、ぜひMyアセットへお越しください。