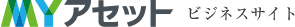外国人による日本の不動産購入規制とは?購入する際の手続きなどを解説
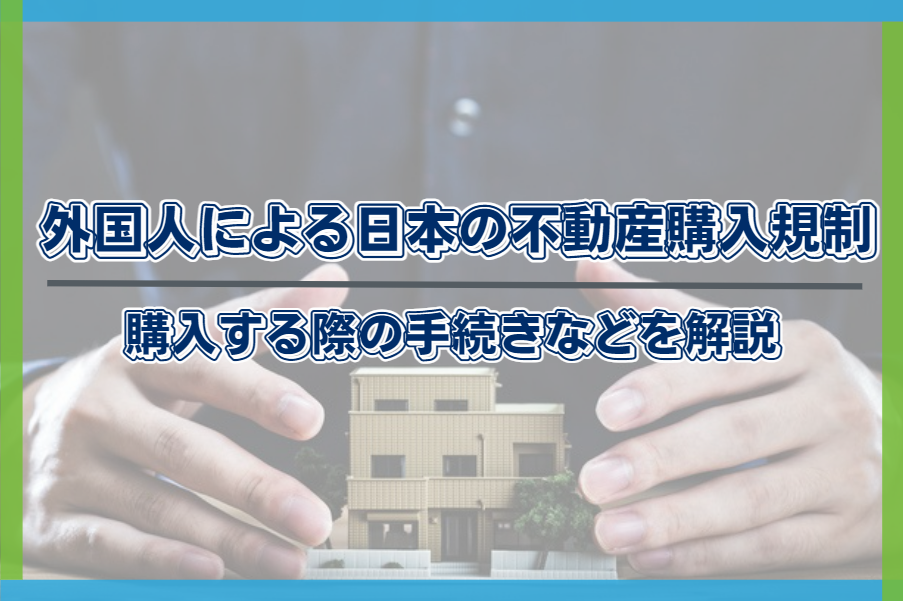
2025年9月3日
目次
近年、日本の不動産市場に注目する外国人投資家が増加しています。円安の影響や安定した経済環境が背景にある一方で、安全保障上の観点から規制の動きも進んでいます。
本記事では、外国人による日本の不動産購入に関するルールと規制、手続きの流れや注意点までをわかりやすく解説します。
日本における外国人の不動産購入の基本ルール
日本では、外国人であっても土地や建物の購入が原則自由に認められています。国籍や居住地に関係なく、売買・贈与・相続といった所有権の移転も可能で、外国人も日本人と同様に不動産の所有権を持つことができます。
ただし、近年では安全保障の観点から規制強化の動きも出ており、「重要土地等調査法」に基づく制度などの理解が求められます。
外国人でも土地・建物の所有が可能
日本では、外国人に対する不動産購入の制限はほとんどありません。 住宅や商業施設はもちろん、土地の所有も可能で、所有期間にも制限はなく、永続的に保有できます。
自由度の高さは世界的に見ても珍しく、外国人にとって日本の不動産市場は非常に開かれた存在です。 そのため、東京を中心に大阪や福岡、北海道、沖縄といった都市部や観光地では、外国人による土地や建物の購入への関心が高まっています。
購入してもビザ・永住権は得られない
不動産の取得は、日本での在留資格や永住権の取得とは無関係です。 つまり、日本に家を買ったからといって自動的に住める権利が付与されるわけではありません。
ビザ取得には別途手続きが必要で、目的に応じた在留資格(例:経営・管理ビザなど)を取得する必要があります。 この点を誤解して購入に踏み切ると後々問題になる可能性がありますので、注意が必要です。
なぜ日本の不動産が外国人に注目されているのか?
日本の不動産市場は、近年ますます外国人投資家から注目を集めています。 背景には、為替状況や経済の安定性、物件の収益性といったさまざまな要因があります。以下に主な理由を整理して解説します。
円安の影響でお得感がある
2020年代以降、円安が進行したことにより、外国人投資家にとって日本の不動産は相対的に「安く」感じられるようになりました。特に米ドルやシンガポールドル、人民元などに比べ円の価値が下がっていることから、同じ金額でも日本では土地が広く高品質な物件を購入できるチャンスが生まれています。
円安の影響で実際に支払う外貨の額が以前よりも少なくて済むという点が魅力です。 この為替の恩恵は、都市部のタワーマンションやリゾート地の別荘など、ハイエンドな不動産を狙う海外投資家にとって大きな動機となっています。
日本の社会情勢が安定している
日本は治安の良さ、インフラの整備、医療制度の充実など、社会的に非常に安定した国と評価されています。 政治的なリスクが低く、急激な制度変更や治安の悪化といった不測の事態が起きにくいため、不動産という長期的な資産運用において安心感が高いのです。
また、地震などの自然災害に対する建築基準も厳しく、特に新築物件は耐震性が高い構造となっています。 こうした要素も、不動産保有に対するリスク管理の観点で外国人投資家の信頼を得る要因となっています。
利回りが高い物件がある
日本の不動産は、他国に比べて投資効率の良い物件が多い点も見逃せません。都市部の賃貸住宅や地方の空き家再生物件など、エリアや用途によっては利回りが4〜8%と高く、安定収入を見込める投資対象となっています。
特に、訪日外国人観光客向けの民泊物件や、法人向けの賃貸オフィスビルなどは、需要の高まりとともに収益性が高い傾向にあります。 円安による購入コストの低下と、高利回りの組み合わせにより、短期間で投資回収できる点も注目の理由です。
海外の不動産規制と日本の比較
日本では外国人による不動産購入に対してほとんど規制がないのが現状です。 この点は、他国と比べても非常に緩やかであり、投資家にとって魅力的な環境となっています。 ここでは、各国の規制状況を2つの分類に分け、日本と比較しながら解説します。
【規制が強い国】
1.中国
・外国人が土地を所有することは不可
・建物の購入は認められるが、土地は国家所有
・居住目的がある場合のみ購入が可能
2.タイ
・外国人の土地所有は禁止
・コンドミニアム購入は建物全体の49%までと制限あり
・法人名義での購入も制限されている
3.カナダ
・外国人の住宅購入を禁止(2023年から施行、一部例外あり)
・空室税や投機税など、非居住者への課税が強化されている
・住宅市場の安定と地元住民の保護を目的としている
【規制が比較的緩い国】
1.アメリカ
・国籍による制限は原則なし
・軍事施設周辺など一部地域のみ事前審査が必要
・登記や税制などの制度も整っており、法人投資にも向いている
2.フランス
・外国人の不動産取得に制限なし
・所有権を完全に取得でき、贈与や相続も自由
・購入によってビザ取得は不可だが、長期滞在の申請は可能
3.シンガポール
・土地や戸建ては規制対象だが、コンドミニアムの購入は可能
・外国人に対して高額の印紙税(最大60%)が課されるが、取得自体は可能
・投資への関心は高く、制度も透明化されている
【日本との違い】
日本では、外国人でも日本人と同じ条件で不動産の所有・取引が可能です。 以下のような特徴があります。
・土地、建物ともに所有権の取得が可能
・所有期間の制限なし
・国籍や在留資格にかかわらず取引可能
・税制も日本人とほぼ同一
日本は世界でも稀な「開放的な不動産市場」と言えるでしょう。 ただし、安全保障上の観点から、「重要土地等調査法」に基づく規制が段階的に導入され始めており、今後は慎重な動向の確認が必要です。
重要土地等調査法とは?
重要土地等調査法は、防衛施設や国境付近など国家の安全保障に関わる地域の土地取引を監視・管理するために定められた法律です。 この法律は2022年に施行され、対象区域内の不動産取引には特定の届出義務が課されるようになりました。 日本人・外国人を問わず、区域内での土地取引や利用に一定の制約が加わることになります。
注視区域・特別注視区域とは?
この法律では、対象となるエリアを「注視区域」と「特別注視区域」の2つに区分します。
注視区域は、防衛施設や重要施設の周囲1km以内の指定された区域、領海防衛上重要な国境付近の離島などが指定され、特別注視区域はさらに重要性が高いエリアです。
これらの区域では、土地や建物の売買において特別な手続きや制限が課される場合があります。
土地などの利用状況調査
注視区域や特別注視区域においては、土地や建物の利用実態について調査が行われることがあります。
この調査には、現地確認、登記簿の確認、所有者や利用者への報告徴収などが含まれます。
目的は、重要施設の機能が妨げられないようにすることであり、特定の行為が「機能阻害行為」と認定された場合は、勧告や命令が下される可能性もあります。
特別注視区域内における届出
特別注視区域に該当する土地・建物の取引では、契約の締結前に内閣総理大臣への届出が義務付けられています。 これは国の安全保障を守るための制度であり、違反があった場合には是正措置がとられる可能性もあります。 以下に概要を整理します。
■届出の対象となる取引の概要
・エリア:特別注視区域内
・物件:面積200㎡以上の土地または建物(各階合計)
・権利:所有権、予約完結権、買戻権などの取得を目的とする権利
・契約:売買、贈与、交換など(予約契約を含む)
■届出の種類と期限
・事前届出:契約締結前に内閣府へ提出(契約予定日前日までに到着)
・事後届出:売買契約成立後、2週間以内に提出(調停・競売・和解等が対象)
■届出が不要なケース
・相続や遺産分割など、契約に基づかない所有権移転
・一部公的機関(独立行政法人など)への譲渡
・他法令により使用目的が審査される取引(例:農地法や公有水面埋立法等の許可契約)
封筒の表には「重要土地 届出書在中」と赤字で記載し、返信希望の場合は切手付きの返信用封筒も同封してください。
このように、特別注視区域での取引では細かい条件や手続きが定められています。対象物件の所在地や面積を事前に確認し、必要な手続きが抜けないよう注意しましょう。
※参照元:重要土地等調査法
外国人が不動産を購入する際の手続きと注意点
外国人が日本で不動産を購入する際には、居住状況や在留資格の有無に応じて手続きが異なります。
トラブルを避け、スムーズな契約を実現するためには、それぞれのケースに応じた正確な準備が必要です。
ここでは、2つのパターンに分けて手続きと注意点を解説します。
日本に居住している・在留資格がある方
日本に居住し、在留カードを持つ外国人は、基本的に日本人と同様の手続きで不動産を購入できます。不動産取引にあたっては、以下の書類が必要です。
・在留カード
・住民票(マイナンバー住民基本台帳)
・印鑑および印鑑証明書(登録済みの場合)
・パスポート(補足書類として)
・特別永住権証明書
また、日本国内の金融機関口座を持っていれば、支払い・ローンの手続きも比較的スムーズに行えます。 住宅ローンの審査では永住資格の有無が重要視される場合が多く、収入や勤務年数、日本語能力も評価対象になります。
注意点として、取得した不動産が投資用である場合、確定申告や納税義務が発生します。 また、物件の所有後は毎年固定資産税・都市計画税が課税され、支払い遅延には延滞税が生じる点にも留意しましょう。
日本に居住していない・在留資格がない方
海外在住の外国人が日本で不動産を購入することも可能ですが、手続きはやや複雑になります。 この場合、以下の書類が必要です。
・外国政府発行書類
・宣誓供述書(住所と署名の正当性を証明するため)
・パスポート(本人確認)
・国内連絡先の情報(2024年より登記に義務化)
・契約時に代理人を立てる場合は委任状
印鑑証明が取得できない場合もあるため、署名の正当性を「宣誓供述書」で補う必要があります。
また、契約・決済・登記の各段階で、日本に来られない場合は、代理人による対応が必要です。
特に「売買契約代理人」「納税管理人」「決済代理人」の3者を早めに選定しておくと、スムーズな取引が可能になります。
さらに、購入後20日以内には「外為法」に基づく報告義務があります。
不動産取得が完了したら、財務省(日本銀行)へ書面にて届け出なければなりません。非居住者が税務上の手続きに対応するのは困難なケースも多いため、納税管理人を立て、確定申告や固定資産税の納付などを代理してもらう仕組みを整えることが推奨されます。
なお、非居住者または外国法人なら日本国内にある不動産を取得した購入者は、原則購入対価の支払い時に源泉徴収を行わなければなりません。
外国人との取引で起こりがちなトラブル
外国人との不動産取引では、言語や文化、習慣の違いにより、日本人同士の取引とは異なるトラブルが発生することがあります。特に不動産業者にとっては、円滑な対応力と正確な情報提供が求められます。 以下では、現場で実際に起こりやすい3つのトラブル事例を紹介し、それぞれの原因と対策を解説します。
コミュニケーションが上手くいかない
外国人との取引では、言語の壁が大きな課題の一つです。 専門用語が多く使われる不動産取引では、正確な意思疎通が難しくなる場面も少なくありません。 例えば、契約内容の誤解や費用に関する認識のズレなどが、後にトラブルの原因となることがあります。
・英語または母国語に対応した通訳を同席させる ・翻訳済みの資料や契約書の提供 ・メールやオンライン会議など、記録に残る形でのやり取りを徹底する
不明点を放置せず、確認を繰り返すことで、相互理解を深めることが大切です。
重要事項説明など契約書を理解できずにクレームになる
契約書や重要事項説明書の内容が十分に理解されていなかったことによるトラブルもよく見られます。
例えば、管理費や修繕積立金、ローンの返済条件などの誤認が後々のクレームにつながることがあります。
契約の場で「同意した」という形式が整っていても、実際には内容を把握していないケースも少なくありません。
このような事態を防ぐには、以下の対応が効果的です。
・日本語を正文とし日本法に基づき行う
・契約書類の和英併記、または翻訳書類の添付
・通訳者による重要事項説明の同席、通訳による記名押印
・海外在住の買主は来日または宅地建物取引が海外へ訪問
法的なトラブルに発展するリスクを避けるためにも、理解確認を丁寧に進める必要があります。
決済がスムーズに進まない
外国人との不動産取引では、決済手続きがスムーズに進まないこともよくあります。 例えば、海外送金の遅延、為替変動による不足金、本人確認書類の不備などが原因となります。
また、日本の銀行口座を持たない非居住者の場合、代理人を介した決済が必要になるため、手続きが煩雑になりがちです。 以下のような備えをすることで防ぐことができます。
・決済代理人(司法書士など)による送金・登記の一元管理
・決済スケジュールの明確化と事前調整
・海外送金における着金確認の余裕を持った計画
・海外送金はエスクローサービスや司法書士、仲介会社の送金の仲立ちが必要
これらの対応により、取引の遅延や不履行リスクを抑えることができます。
不動産売買のご相談はMyアセット
Myアセットでは不動産売買のサポートを行っております。 首都圏エリアを中心に、不動産投資の専門家が一人ひとりのお悩みに寄り添い、売買タイミングと価格をご提案いたします。 不動産売買のご相談はMyアセットにお任せください。
まとめ
日本の不動産市場は、外国人にとって取得条件が非常に緩やかで、投資先として高い注目を集めています。 土地・建物の所有に制限はなく、円安や高利回り物件の存在が人気の背景です。 一方で、安全保障上の観点から「重要土地等調査法」による規制が進んでおり、特別注視区域での取引には事前届出が必要になる場合もあります。
また、在留資格の有無によって購入手続きが異なり、誤解や手続き不備によるトラブルも少なくありません。 信頼できる専門家と連携し、制度を正しく理解することが、スムーズな取引につながります。