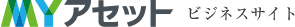オーナーチェンジの不動産に投資するメリットやデメリットは?

2022年08月26日
ここでは、オーナーチェンジの不動産投資について詳しく解説しています。買主にとってお得な要素もあるオーナーチェンジですが、購入する際には、デメリットや注意点も踏まえ、慎重に検討していきましょう。
オーナーチェンジで引き継がれる権利や義務などもあわせ、以下ではオーナーチェンジの注意点やメリット・デメリットを詳しくご紹介します。
オーナーチェンジの不動産とは
オーナーチェンジとは、賃貸入居者がいる状態の物件を売買することを言います。初回の入居者募集の手間や不安がなくなる点では、買主にとって有利な取引となりますが、実際に購入する際には、物件の過去の実績や売却理由を確認しておくなど、いくつかの注意点があります。
オーナーチェンジの対象物件は、マンションの1室だけのこともあれば、マンションやアパート1棟まるごとのこともありますが、あくまでも「賃貸入居者がいること」が前提での取引を指します。例えば、1棟まるごとのマンションの中に1人でも賃貸入居者がいればオーナーチェンジとなりますが、賃貸入居者が1人もいない場合にはオーナーチェンジとはなりません。
購入の際は過去の実績や売却理由を確認するべき
物件に賃貸経営の実績がある
入居者募集の手間を省ける
オーナーチェンジの不動産に投資をするメリットの一つが、入居者募集に必要な各種の手間を省ける点です。
通常、入居者募集には、ある程度のリフォーム、募集広告の作成・依頼、賃料や契約内容の設定、入居者の審査などが必要となりますが、すでに賃貸入居者がいる以上、これらの手間は一切かかりません。手間だけではなく、時間もコストも節約できます。何より、入居者の不安なく不動産経営をスタートさせられることは、買主にとって大きなメリットに感じられるでしょう。
物件購入直後から家賃収入を得られる
まだ入居者の決まっていない物件に投資をした場合、購入後、いつ入居者が入るのか分かりません。募集のタイミング等によっては、入居者が決まるまでに数ヶ月かかることもあります。入居者を待っている間も、ローンの返済などのコストは掛かり続けます。
一方でオーナーチェンジの不動産に投資をした場合には、すでに賃貸入居者がいる形なので、物件を購入した初月から家賃収入を手にすることができます。購入直後から不動産投資の醍醐味を実感できるでしょう。
相場より安い価格で購入できる物件がある
相場よりも安く家賃を設定している物件をオーナーチェンジで購入した場合、家賃収入が少ないという理由で、物件価格そのものも安く設定されていることがあります。
あえて、このような物件を購入しておけば、将来的に入居者が入れ替わるタイミングで家賃を相場通りに設定しなおすことで、以後は利回りが上がります。相場より安く買った物件から、相場通りの家賃収入を得られる格好です。
確認すべき売却理由
特に問題のない売却理由
物件そのものや契約中の入居者などに問題がない場合には、基本的に購入しても大きな問題は生じないケースが大半です。
例えば地主大家が売主であるケースでは、自身の老人ホーム入居などの費用に充てる理由で売却することがあります。物件や契約中の入居者に何らかの問題があって売却するわけではないので、購入しても大きな問題は生じないでしょう。
他にも、相続人が売却するケース(相続税納税に迫られた売却)、所有期間が5年超で売却するケース(税金対策に基づいた計画的売却)なども、物件等の問題で売却するわけではないことが想定できるため、購入しても大きな問題は生じにくいと思われます。
購入を見送ったほうが良い売却理由
逆に、物件そのものや契約中の入居者などに問題がある場合には、円滑な不動産経営ができなくなる恐れがあるため、購入を見送るのがおすすめです。
例えば、同じマンション内にある部屋にも関わらず、どうしても空室になりがちな特定の部屋があることがあります。日当たりや間取りなどが原因で入居者が住みにくさを感じていることが、早めに転居されてしまう主な原因です。過去の入居履歴から、入居者の平均契約期間を確認しておきましょう。
オーナーと入居者が係争中の物件や入居者から賃料減額交渉を受けている物件、同じマンション内にトラブルメーカーがいる物件などは、購入を避けることをおすすめします。
オーナーチェンジで引き継がれる権利と義務
オーナーチェンジは、賃貸入居者がいる状態での不動産売買となるため、新オーナーには、旧オーナーと入居者との間に存在した権利や義務が引き継がれます。引き継がれる具体的な権利・義務を確認しておきましょう。
新オーナーに引き継がれる権利
新オーナーには、次の3つの権利が引き継がれます。
- 契約中の入居者から賃貸料を受け取る権利(民法第601条・改正民法第601条)
- 契約終了時の入居者から物件を返還してもらう権利(民法第597条・改正民法第601条)
- 契約終了時に入居者に対して原状回復を要求する権利(民法第598条・改正民法第621条)
新オーナーに引き継がれる義務
新オーナーには、次の3つの義務が引き継がれます。
- 契約中の入居者に物件を使わせる義務(民法第601条・改正民法第601条)
- 建物の修繕をする義務(民法第606条・改正民法606条)
- 入居者の退去時に敷金を返還する義務(判例のみ・改正民法第622条のみ)
改正民法による変更点
平成29年に交付された改正民法が、令和2年4月1日より施行されています。この改正民法では不動産賃貸に関する規定も改正され、これに伴ってオーナーチェンジ物件の権利・義務関係にも変更が生じています。
【改正民法による変更点】
- 民法第606条 – 賃貸人による修繕等
- 民法第611条 – 賃貸物の一部滅失等による賃料の減額等
- 民法第621条 – 賃借人の原状回復義務
- 民法第622条の2 – 敷金
出典:法務省|民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
民法第606条 – 賃貸人による修繕等
改正前の規定では、物件の使用等に必要な修繕の義務をオーナーが負うものとされていました。改正後の規定でも、原則として修繕の義務はオーナーが負うことになりますが、入居者の責任で生じた修繕については「この限りではない」との例外規定が加わっています。
民法第611条 – 賃貸物の一部滅失等による賃料の減額等
改正前の規定では、物件の一部が入居者の過失なく滅失した場合には、入居者はオーナーに対し、滅失した部分の割合に応じて賃料の減額を請求できるとされていました。
改正後の規定では、滅失だけではなく「その他の事由」も加わり、かつ「入居者がオーナーに賃料減額を請求できる」ではなく、「請求を待たずして当然に減額される」との内容に変更されています。
民法第621条 – 賃借人の原状回復義務
改正前の規定では、入居者の原状回復義務について「原状に復して」という簡素な表現しか存在しませんでした。この簡素な規定の一般的な解釈により、入居者は賃貸契約終了時に原状回復義務を負うのが原則とされていました。
改正後の規定では、これまでの原状回復義務の一般的な解釈が明文化されています。加えて、物件の損傷に対し入居者の過失がない場合には、入居者は原状回復義務を負わないとする規定も設けられました。
民法第622条の2 – 敷金
改正前の民法では、敷金に言及する規定は存在したものの、敷金に関する法律関係を定めた規定は存在しませんでした。
改正後は、これまでの判例や学説を踏まえ、従来一般的解釈とされてきた敷金に関する法律関係が、明確な規定として定められています。
今回のまとめ
賃貸入居者がいる状態の物件を売買するオーナーチェンジは、通常の不動産購入時とは異なるメリットだけでなく、注意すべき点もあります。主な注意点は、前オーナーから引き継がれる権利・義務などです。
Myアセットでは、オーナーチェンジを含めた多くの投資用不動産の取り扱い実績がございますので、不動産投資のプロとして、お客様のニーズに合った的確なサポートをさせていだきます。
不動産投資が初めての方から、すでに投資をされている方まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。